鉢について
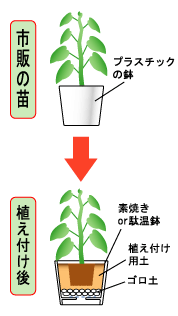 買ってきたばかりのベゴニアはプラスチックの鉢に植わっているはずです。これは生産者のハウスでの生産効率と、流通上の問題から使われているのですが、決してよい容器ではありません。買ってきたらまず素焼きか、駄温鉢に植え替えましょう。素焼きはベージュ色をした軽くてもろい鉢で、洋蘭によく使われます。駄温鉢は普通に園芸店で売っている茶色の鉢でふちに艶を出した焼き方をした、ごく一般的な鉢です。 買ってきたばかりのベゴニアはプラスチックの鉢に植わっているはずです。これは生産者のハウスでの生産効率と、流通上の問題から使われているのですが、決してよい容器ではありません。買ってきたらまず素焼きか、駄温鉢に植え替えましょう。素焼きはベージュ色をした軽くてもろい鉢で、洋蘭によく使われます。駄温鉢は普通に園芸店で売っている茶色の鉢でふちに艶を出した焼き方をした、ごく一般的な鉢です。
どちらも古いものや、苔が生えているようなものは熱湯消毒し、さらに日干しにして十分乾かしてから使うようにします。
とりあえず熱帯夜が続く時点では体力を消耗させる本格的な植え替えは避けたほうが無難です。根ぐされを防ぐために、プラスチックに植わっているものは、素焼きか、駄温鉢に入れ替えます。
鉢の大きさは寸のもの、号のもの、センチのものとあってややこしいのですが、どちらも一寸(一号)=3センチと考えれば間違いありません。鉢の底に必ずサイズが書いてありますから、同じ大きさのものに、根鉢を崩さないようにして入れ替えます。
お勧めとしては素焼きの鉢で、素焼きの良いところは、鉢の中の水分が多くても、鉢の壁が吸い、外側の表面から蒸発することによって鉢の中の温度を下げるとともに、水分量もちょうど良い状態にしてくれるからです。 |
用土について
買ってきたものは、用土を崩さないように、そのままで鉢だけ前記のものに替えれば、とりあえずはどんな用土でも大丈夫です。特にピートモス系の用土に植わっているプラスチックの鉢のものは必ず鉢を替えるようにしましょう。
用土の配合は種類によって違ってきますが、基本は水はけが良くて軽めの用土に仕上げる事です。大きくなる種類は若干重めにします。自分で用土を混ぜ合わせる場合は後から同じように作れるように出来るだけ分かりやすく単純な組み合わせにしましょう。一般的な配合例として<ピートモス[3]、赤玉土[3]、バーミキュライト[3]、鹿沼土[1]>などが使われます。実際は育てながら環境にあった配合を見つけると良いでしょう。
●土の種類と特徴
- 赤玉土<あかだまつち>
基本用土のひとつで、粒上で指で軽く押すと崩れます。元は関東ローム層の赤土を粒状にして、通気性を向上させてあります。水はけが良く園芸用土として適しているため広く利用されています。粒の大きさによって小粒、中粒、大粒の3種類に分類されて販売されています。ただし、長い間使用していると粒が潰れて通気性・水はけが悪くなるので注意が必要です。
- 鹿沼土<かぬまつち>
弱酸性の火山灰土で、見た目は赤玉土ににています。栃木県の鹿沼地方で取れるため、この名前がついています。水はけの良い園芸用土に適した土ですが、長期の使用は粒が潰れて通気性・水はけが悪くなるので注意が必要です。通常、細かくなった土をふるいにかけてから使用しますが、最初から細かい部分を除いて販売されている物もあります。
- 腐葉土<ふようど>
葉が中程度分解されたもので、水はけや通気性に優れており、土を柔らかく仕上げる事ができます。これが更に分解したものを堆肥と呼んで区別してあり、こちらは肥料として使います。
- ピートモス
シダや水苔などの植物が分解したものです。酸性の強い土です。非常に軽いため、土を軽く仕上げたいときに使います。通気性・水もちが良い土で根に十分な酸素を供給します。
- パーライト
とても軽い用土で、真珠岩を人工的に高温で膨張させて作ってあります。見た目は白灰色の粒状で、指で簡単に潰せます。水はけを良くしたり、土を軽くしたいときに使います。さし木の用土としても使用します。
- バーミキュライト
パーライトと同じく、人工的に鉱石を膨張させた用土です。見た目は金属のようにキラキラ光っていて、筋が見えます。とても軽くて通気性・水はけ共に優れた用土です。
- 水苔<みずごけ>
その名の通り、水苔を乾燥させたものです。テラリウム栽培の時などに鉢のまわりに敷いて乾燥を防ぐ目的で使います。
協力:山口裕美子さん |