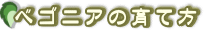 |
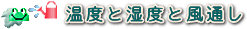 |
温度について
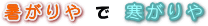
|
|
|
|
|
|
30℃を超えると生長が止まる |
|
|
生育適温は15℃〜25℃ |
|
|
|
|
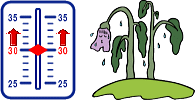 |
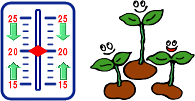 |
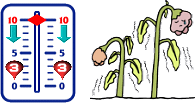 |
|
|
|
|
ベゴニアは熱帯から亜熱帯に分布するので耐寒性に欠けわが国での屋外越冬は難しく、10℃を下回ると生長が止まり、3〜0℃で枯死するものが大部分である。また、暑すぎるのにも弱く、30℃を超えると生長が止まる。ベゴニアの種類によって致死温度は異なるが、生育適温は15℃〜25℃で温度の面から見ると人の快適温度とよく似ている。
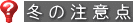 |
屋外のベゴニアは、11月中旬までに室内へ取り込む。
秋に挿し木をして苗の状態で取り込むと多くの種類が保存できます。 |
|
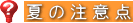 |
なるべく涼しい場所を見つけて、夕方周囲に打ち水をするなどの工夫で夏越しをする。
遮光ネットも遮熱効果があるものを使用すると良いでしょう。
強度の遮光で温度の上昇を押さえたほうが、夏越しの傷みを少なくします。 |
|
|
湿度について

|
|
|
|
|
|
70%以上の湿度の高い環境が適している |
|
|
空気が乾燥してくると
うどんこ病やダニが発生しやすくなる |
|
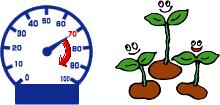 |
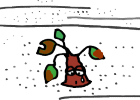 |
|
|
|
特に生長期は蒸散が盛んで、乾燥しがちになる。湿った空気が流れる場所が理想だが、加湿器を上手に使えば可能だろう。

【11月〜4月にかけて】
空気湿度は70%を切ることが多いのですが、生育が緩慢か停止している時期なのでそれほど気にしなくても大丈夫です。
ただし、暖房中の乾燥した室内に取り込んだ場合、加湿器を使うのもいいですが、ビニールで囲むだけでも効果はあります。
小苗は熱帯魚の水槽に入れて窓際に置くとよいが、ワーディアン・ケースがあればさらによい条件になります。
また、休眠のまま冬越しする場合と、温度が保てて生長を続けている場合とは区別して管理します。
温度が保てて生長を続けている場合は、霧吹きをするなどして湿度を保つようにするとよいでしょう。 |
【5月〜10月にかけて】
空気湿度は70%を超えますが、最近は異常気象続きで、高い温度が続いたり、乾燥状態が続いたりで臨機応変に対応しなければなりません。
鉢の間隔をやや密にして、湿度を保つようにした方が調子はよいのですが、生長してすぐ過密になるので、常に注意して鉢間隔を広げていかないと失敗します。
風通しの良い場所に置くという表現は実に捕らえにくいし、風速何メートルというのも難しい。
しかも湿った風と乾いた風では根本的に異なるのです。
ベゴニアは風に当たっても強い方の植物だが、空気が乾燥してくるとうどんこ病やダニが発生しやすくなります。実は湿度と通風は深く係わっているのです。 |
|
|

↑ クリックしてください ↑
鉢の表土が乾いてから、たっぷり水をやるというのが原則です!
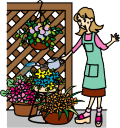 |
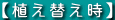
充分水をやるが次は必ず表土が乾いてからにしないと根腐れを起こしてしまう。
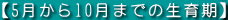
木立性ベゴニアや根茎性ベゴニア
頭から葉水を、葉裏から散水しても大丈夫。もちろん、根元にも充分与える。
球根ベゴニアやエラチオール・ベゴニア
腐りやすいので、午前中に、水差しで株元に注ぐように与える。
乾燥しすぎると・・・水やりしても鉢の縁に沿って流れてしまい土全体に水が行き渡らないことがある。このような時は、水を溜めた中に、しばらく鉢を縁まで漬けて全体に給水させる。
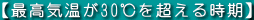
最温度を下げる意味で、水やりは夕方にする。葉裏や周辺にも散水する。
低温期の水やりは、晴れた日の午前中にするようにして、過湿にならいように注意する。
葉がいつまでも濡れていると、ポトリチス病が発生しやすくなる。 |
|
|
|
風通しについて
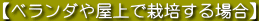 |
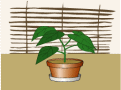 適度な湿気を含んだ微風が通るところが理想です。 適度な湿気を含んだ微風が通るところが理想です。
よしずや波板で風を遮らないとうまく育ってくれません。
また、空気がまったく動かないとよい生長は望めない。 |
|
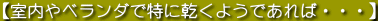 |
| バットに砂利石を敷き、水を溜め、その上に鉢を並べるとか、ベランダには人工芝を敷くと周囲の湿度も高まります。 |
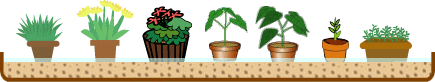 |
|

散水や噴霧、加湿器などで容易にできます。
過湿には通風を図ることで解決できます。
いずれにしても急激な変化の無い状況を維持することが大切です。 |
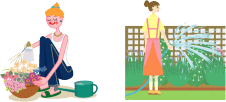 |
|
|
 HOMEへ戻る HOMEへ戻る
このサイトはInternet Explorer 5.0以降にてご覧下さい。
Copyright (C) 2001 Begonia-net All rights reserved. |