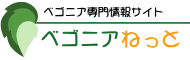メインメニュー

 HOME HOME

 ベゴニアとは? ベゴニアとは?
 ベゴニアの育て方 ベゴニアの育て方
 ベゴニアの管理 ベゴニアの管理
├季節の管理:夏
├季節の管理:秋
├球根の初期管理
├球べゴの夏越し
├エラチの切り戻し
├テラリウム栽培
├増やし方(1)
└増やし方(2)
 ベゴニア図鑑new! ベゴニア図鑑new!
 今週のベゴニア 今週のベゴニア



栽培日誌

>>栽培日誌を見る
「ねっと」とともにベゴニアの勉強し、花が咲いては喜び、ダメにしては落ち込みまだまだな〜と実感しています。ちょっと頑張って、私流の栽培日記です。

レポート・訪問記

 ベゴニア訪問記 ベゴニア訪問記 ├ベゴニア園を訪ねて
├自生地を訪ねて
├生産者を訪ねて
└愛好家を訪ねて
 イベントレポート イベントレポート
 ねっと主催イベント ねっと主催イベント
 ベゴニアスポット ベゴニアスポット

コミュニティ

 掲示板 掲示板
├情報掲示板
└画像掲示板★
(利用方法)
 管理人コーナー 管理人コーナー
├気ままにベゴニア
├気まぐれ日記
└ツイッター
 リンク集 リンク集


植村先生特集

日本ベゴニア協会長の植村猶行 先生の作出品種の紹介。
>>記事はこちらから
|
|
植村猶行先生(日本ベゴニア協会会長)作出品種特集
日本ベゴニア協会会長 植村猶行 先生が2006年8月12日ご逝去されました
2006年初頭から入退院を繰り返しされていましたが、4月にご自宅にお電話させていただいた時はお元気なお声でしたので、急なお知らせに驚きました。とても大切な方を失ったという悲しみでいっぱいです。
ご冥福をお祈りします
|
植村先生の作出品種
 日本ベゴニア協会長 植村猶行 先生 日本ベゴニア協会長 植村猶行 先生
日本ベゴニア協会は1962年5月創立で今年で43年になります。
私が入会したのは1995年10月で若い時の植村先生を残念なことに存知あげませんでした。
その上、勉強不足で先生の作出されたベゴニアも身近に見ていたのに、そのベゴニアが先生の作出されたベゴニアであることを知る事ができたのは、チェックリストが出版されたことと「ベゴニアねっと」を始めて勉強するようになってからです。

オオイズミ
(1971)
|

ドレッシー
(1966)
|

ピノキオ
(1970)
|

ヒトミ
(1972)
|
現在も育てられ後世に残るすばらしいベゴニアを先生が作出されていたことを改めて知りました。
協会に入り植村先生の印象は いつお会いしてもニコニコ穏やかな顔をされています。「ベゴニアねっと」主催のヨコハマプリンスホテルのベゴニア展には、ご自宅から遠いのにもかかわらず毎回来てくださいます。
いつもカメラをお持ちで ゆっくり時間をかけてベゴニアの写真を撮って帰られます。
最近では親しみをもって先生のことを身近に感じられるようになりました。
これからも健康に留意して私どもにご指導いただけることを願っています。
|

ルバーシィ
(1966)
|

ピコティー・シャンデリア
(1983)
|

ピンク・シャンデリア
(1977)
|

ホワイト・シャンデリア
(1982)
|
333,333hit時に植村先生よりお祝いを頂きました
ベゴニアねっと参加者333,333人突破おめでとう
私はホームページを開設していませんが、家内のものを留守中に開いてみることがある。幾つかのベゴニア園の紹介が見られ、中でも「ベゴニアねっと」は内容が豊富で、ついつい長時間付き合ってしまう結果になります。
最近では毎日500人近くの方が訪れているようです。それにしても、この人気の秘密は何でしょう。
思うに、美しいベゴニアの写真が多いこと、しかもこれが適当な間隔で更新されていること、その上、ベゴニアに関する情報が手軽に得られて便利、また、情報交換欄があって、初心者の質問に専門家が答えるシステムが管理人のTomieさんの親切なアドバイスと共に、上手に運営されているからだろう。
そして、業者としての売らんかな臭や、押し付け、教えてやるぞと言わんばかりの横柄さなど微塵も感じさせない。明るく、華やかな雰囲気に満ちている画面構成が効果を発揮しているのだろうか。ちょっと理屈っぽい話になってしまったけど、横浜プリンスホテルの年2回の展示会とあわせて、魅力いっぱいの植物「ベゴニア」の宣伝ウーマンとしてのご活躍に感謝し、ねっとへの参加者333,333人突破を記念して、お祝いと激励の言葉とします。
 HOMEへ戻る HOMEへ戻る
|
 日本ベゴニア協会長 植村猶行 先生
日本ベゴニア協会長 植村猶行 先生